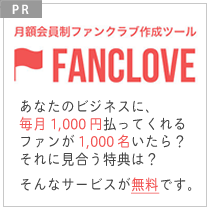明智光秀丹波進攻と福知山
天正三年(1575)六月信長に丹波進攻を命じられ、丹波進攻を進めていた明智光秀は、丹波氷上郡黒井城の荻野直正を最初に攻めましたが、織田信長に恭順していた多紀郡八上城主波多野秀治が、突如背いて光秀軍に襲い掛かり大敗した光秀軍は京都に逃げ込み、その後坂本城に帰城しています。この波多野秀治の裏切りについては、丹波に支配力を強化しょうとする波多野氏と信長の勢力の伸長を恐れる毛利氏の働きかけが背後にあり、両者の利害が一致した結果と考えられます。やがて信長と毛利氏の対立が激化すると、天正五年、織田信長は、羽柴秀吉に中国進攻を命じ、一度失敗した明智軍は、再度丹波氷上、多紀郡の攻略を開始しました。明智光秀は、細川藤孝を、副将としてぞくぞくと丹波へ軍勢を送り込み、最初の丹波進攻に裏切られた波多野秀治の居城八上城の攻略に取り掛かりました。
明智光秀は、丹波攻略の最中にもかかわらず、織田信長の要請により各地の戦いに参戦しています。天正四年(1576)四月には、石山本願寺との天王寺山の戦いや、天正五年(1577)には、雑賀攻めに参戦し、同年十月には、信貴山城の戦いに参戦して城を落としています。天正六年(1578)四月二十九日には、毛利攻めを行う秀吉の援軍として播磨国へ派遣され、六月に神吉城攻めに加わって戦っています。
天正六年十月下旬には、織田信長に背いた荒木村重を攻めて有岡城の戦いにも参戦しています。丹波攻めと各地への転戦の往復を繰り返す明智光秀は、ようやく丹波攻めに専念し、八上城の攻略に取り掛かりました。八上城は、丹波富士と称される高城山に築かれた山城で、丹波戦国大名波多野氏の居城であり、麓からの高さが200Mを超すという要害に守られており、攻めにくい山城でであった。秀治の代に至って本丸、二の丸、三の丸、岡田丸を構築し、歴史に残る難攻不落の山城につくり替えています。天正三年から天正七年にかけて、明智光秀、羽柴秀長らの大軍による丹波攻めが始まり、前後11回にわたる攻撃にも八上城はゆるがなかったと言われています。光秀は八上城を、長期に渡り、取り囲む兵糧攻めを行い、この徹底した包囲戦により八上城はの補給路は完全に断たれ、城内では餓死者が続出したそうです。秀吉の「干殺し」にも勝るとも劣らない悲惨な光景が現出したそうです。天正七年(1579)七月落城し、波多野氏は滅亡しました。
ここで八上城落城について、篠山曽地村に残る落城秘話について、お話しておきます。明智光秀は、織田信長の命令で、丹波国八上城を奪い取ろうと、天正七年(1579)八上城を包囲して、食べ物を運び込む道をふさぎ、兵糧攻めにしょうと考えました。ここ数日もすれば兵糧がなくなるので城から二人、三人と逃げて出てくる者があるだろうと監視の目を光らせていました。所が十日たっても二十日たっても、一人も出てきません。不思議に思った明智軍は、八方に探りの手を伸ばし、見張っていました。
その時、曽地村の寺々から、山の尾根伝いに、笈に米、味噌を詰めて兵糧を運ぶ修行僧を見つけ取り押さえました。明智光秀は、怒って放火隊を繰り出して、まず四十九院に火を放ち寺を次々に焼いていきました。明智軍は寺から兵糧をはこんでいたお坊さんの首を次々にはねて、その場に掘った穴のなかへ葬りました。曽地川沿いの刑場跡に供養塚が安置されている。村びとたちが今も活ける草花が、瑞々しくおもえた。
光秀は、八上城落城後、直ちに第二次黒井城攻めを開始します。天正三年(1575)の第一次黒井城の戦いについては、明智光秀軍は圧倒的兵力で黒井城を包囲し戦況は明智光秀軍が有利であった。しかし攻城戦開始後二ヶ月以上が経過した翌天正四年(1576)一月十五日信長に恭順していた波多野秀治が突如三方向から攻め立て明智軍は総退却となり明智軍の敗戦となりましたが、第二次黒井城の戦いにおいては、赤井悪衛門直正が、癌により亡くなり、その後、赤井忠家に代わり、赤井忠家軍は、第一次黒井城の戦いの時は違い、波多野家からの援軍もなく、黒井城の支城もほとんど落城していまい、兵力も激減していたと思われます。翌天正七年(1579)三月に八上城と黒井城の分断を目的に金山城を築城します。金山城築城により分断の効果があり、又、主曲輪には僅かな手勢しか置いておらず、忠家も奮戦したが、最後は自ら火を放ち敗走しました。天正七年八月黒井城は、ようやく落城しました。
明智光秀軍は、多紀郡、氷上郡を平定し、その後、天田郡、何鹿郡に進攻を、開始します。
(1)明智光秀天田郡、何鹿郡に進攻
明智光秀は、氷上郡、多紀郡を平定後、天正七年に天田郡に侵攻しました。侵攻が始まる当時の状況は、丹波三郡といいまして、氷上郡(丹波市)天田郡(福知山市)何鹿郡(綾部市)を奥三郡と呼んでいました。当時、天田郡(福知山市)の状況は、塩見頼勝が支配していました。塩見頼勝は、横山城に嫡男(頼氏)奈賀山城に次男(長員)猪崎城に三男(利勝)和久城に四男(長利)牧城に五男(利明)を配置して、天田郡を、支配している状況でした。
この塩見一族は、氷上郡の荻野直正、多紀郡の波多野秀治の勢力下におかれていたようで、明智光秀が、氷上郡(丹波市)・多紀郡(篠山市)へ進攻し、荻野直正、波多野秀治を討伐し、その後、天田郡、何鹿郡に侵攻しましたので、当地を平定することにつきましては、大きな戦いもなく短期間で平定されたと思われます。
その後、明智光秀は、さらに細川藤孝と協力して一色氏が勢力支配していました丹後へ進攻し丹後の国も平定しています。光秀軍は、非常に苦労して、天正三年より天正七年まで五年の歳月をかけて丹波国を平定したことを、天正七年十月安土城において信長にほうこくしている。織田信長は、明智光秀の丹波での働きを武功第一とし、次に羽柴秀吉の播磨その他諸国での戦功を称している。この功績で、天正八年(1580)に近江国坂本(五万石)と丹波一国(約二十九万石)を加増され計三十四万石を領する大大名になりました。又信長は、天正九年八月二日丹後国を細川藤孝に宛がっている。
(2)福知山城築城の歴史
福知山城は、小笠原長清の末柄とされる福知山地方の国人塩見頼勝が、八幡山の脇に掻上城を築城したのいが始まりと言われています。塩見頼勝は後に性を横山に改め、さらに城主はその息子である塩見信房へと代替わりし、城名も横山城となります。横山城を攻略した明智光秀は、この地を平定し、「福知山(当時は福智山)と命名しました。
福知山城築城の際、福知山城築城図に「〇此相印(ここそういん)曲輪明智光秀作△曲輪細川玄旨(げんし)作」と書かれ、〇が二つ△が一つ印されています。これは、福知山城築城の際,細川藤孝が築城を手伝ったことがわかります。また宮津市史の資料編に、細川藤孝が織田信長に宮津に居城を要請した手紙の返事があり、信長は光秀へも手紙を出しておく、相談して丈夫に作ることが肝要と返事しています。
手紙の内容「ついては、そのふしんのぎ、いそぎたくにそうろう、すなわち、これとうかたえも、しゅいん、つかわすの、そうろうあいだ、そうだんして、じょうぶに、もうしつけるべき、かんようそうろう」丹波、丹後を二人で戦った様子がしのばれます。
福知山は北東に向かえば北陸へ続き、西は山陰へと繋がる丹波の要衝です。そして、日本海へと注ぐ由良川を天然の堀として、盆地中央の大地に築かれたのが福知山城です。今も石垣の一部に光秀公と当時のものが残っています。ちなみに天守台などの石垣は、野面積、あるいは穴太積といわれる技法で積まれています。石垣の間に隙間があって、一見乱雑に見えますが、石材は奥に長く組み入れられ、強固な造りになっています。実は、石積みの基礎の上に天守や櫓を建てるという近世城郭の特徴となる形式は、鉄砲での攻防戦に備えて、明智光秀が近江の坂本城築城で最初に取り入れたものと言われています。元亀二年(1571)の事と言われています。この石積みの技術の持ち主が、坂本穴太の石工たちであり、穴太積の呼び名はここに由来しています。その後、天正四年(1576)築城の織田信長の本拠、安土城においてもこの技術が導入され、以後近世城郭の基本となったようです。
それら光秀がかかわった石垣は、すでにうしなわれ、当時の姿を残す福知山城7の石垣は貴重なものと言えるでしょう。光秀の福知山城の築城は、相当に急いで行われたことを、当時の姿を今に残す天守台の石垣が、語っています。石垣の石材の中に宝篋印塔や五輪塔などの転用石が数多く見られるのであります。発掘調査で見つかった石垣内部に埋め込まれたものと合わせると、五百個余りが使われたようです。これらは、「転用石」と呼ばれるもので、福知山平定後、築城を急ぐ光秀が、資材を周辺の三里四方にある寺院や屋敷跡から集めたと言われています。こうしたことから「光秀は墓石を強奪して城を築いた」と見る人もいますが、必ずしもそうとも言い切れません。光秀は、資材を接収する一方で、その補償も行っています。福知山市上佐々木の野際という地域の共同墓地に「石龕」という代用の墓が今も残っています。それは小さな供養の墓塔を板状の石で囲んだもので、家の形になっています。地元の長老の話に、『大けいまにあいそうな墓石は、徴発して城の石垣にしたんじゃが、その代わりにいうて、この家形の墓を光秀はんがくれたんじゃ」との聞き伝えが、上佐々木の野際地域に残っています。明智光秀は、福知山城築城後、接収した墓石や五輪塔の代わりにこうした石を配り、補償しています。これを「石龕」(せきがん)とよんでいます。
征服者に対する抵抗を少しでも和らげようと、心を砕いた光秀の姿が目に浮かびます。またよく考えますと、当時は檀家という制度がなかったので、誰もが寺に墓があるわけではありませんでした。墓があったのは、土豪クラス以上の有力者のみでしょう。激しく抵抗を続ける土豪を平定する以上は、拠点にあった寺も当然攻撃対象になるわけで、戦乱の後に転がっている墓石を築城に用いたのです。
「征服者」に対する抵抗を少しでも和らげようと、心を砕いた光秀の目に浮かびます。またよく考えますと、当時は檀家という制度がなかったので、誰もが寺に墓があるわけではありませんでした。墓があったのは、土地の土豪クラス以上の有力者のみでしょう。激しく抵抗を続ける土豪を平定する以上は、拠点にあった寺も当然攻撃対象となるわけで、戦乱の後に転がっている墓石を築城に用いたのです。
明智光秀は、福知山を、平定した後、領民の生活を守ることを第一する統治をおこないました。城下の東を流れる由良川は、福知山付近で南東から注ぎ込む土師川と合流していますが、大雨が降ると、その都度城下町の半分以上が水没する事態にさらされていました。そこで光秀は、城下を守るため福知山城から西北に向かって、蛇ヶ端から鋳物師町までの500mわたり、洪水を防ぐ堤防をを築いたと言われています。今でも残っており、現在「蛇ヶ端御藪」と呼ばれています。また水害と戦乱によって荒廃していた福知山の惨状を目の当たりにした光秀は、領民を優遇する思い切った政策取りました。当時屋敷に対して地子銭「屋敷税」がとられていたのですが、光秀はこれを思い切って免除したのです、「地子銭免除といいます」それは統治の前に、町の復興を最優先に考えられたからでしょう。光秀は、福知山に城代として娘婿の秀満を置きますが、秀満も光秀の方針をしっかりと踏襲しています。
高い租税率と戦乱に生活を圧迫された民衆は救世主の到来を待ち望んでいました。
こうして領民思いの光秀の姿が、「占領者」であるにもかかわらず、民衆から絶大な支持を得ることに成功します。